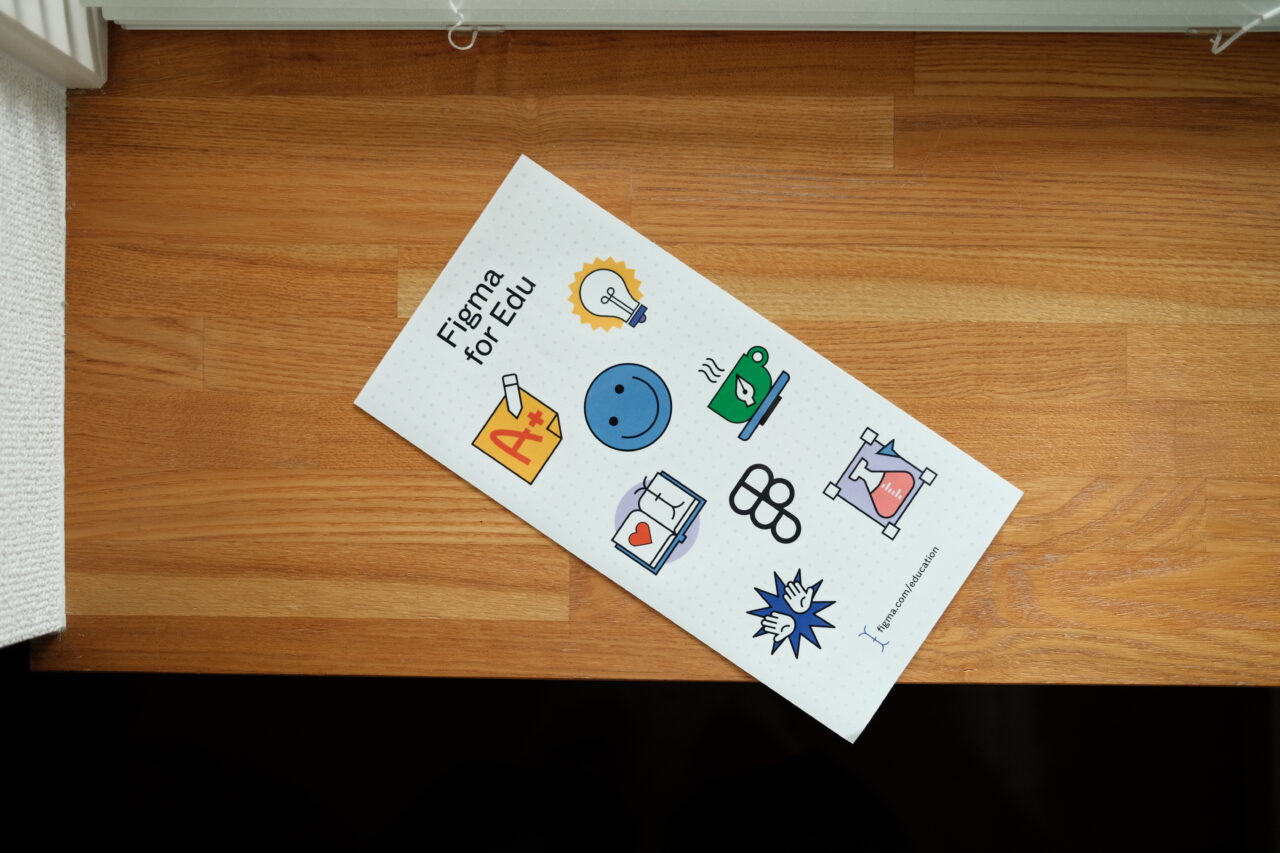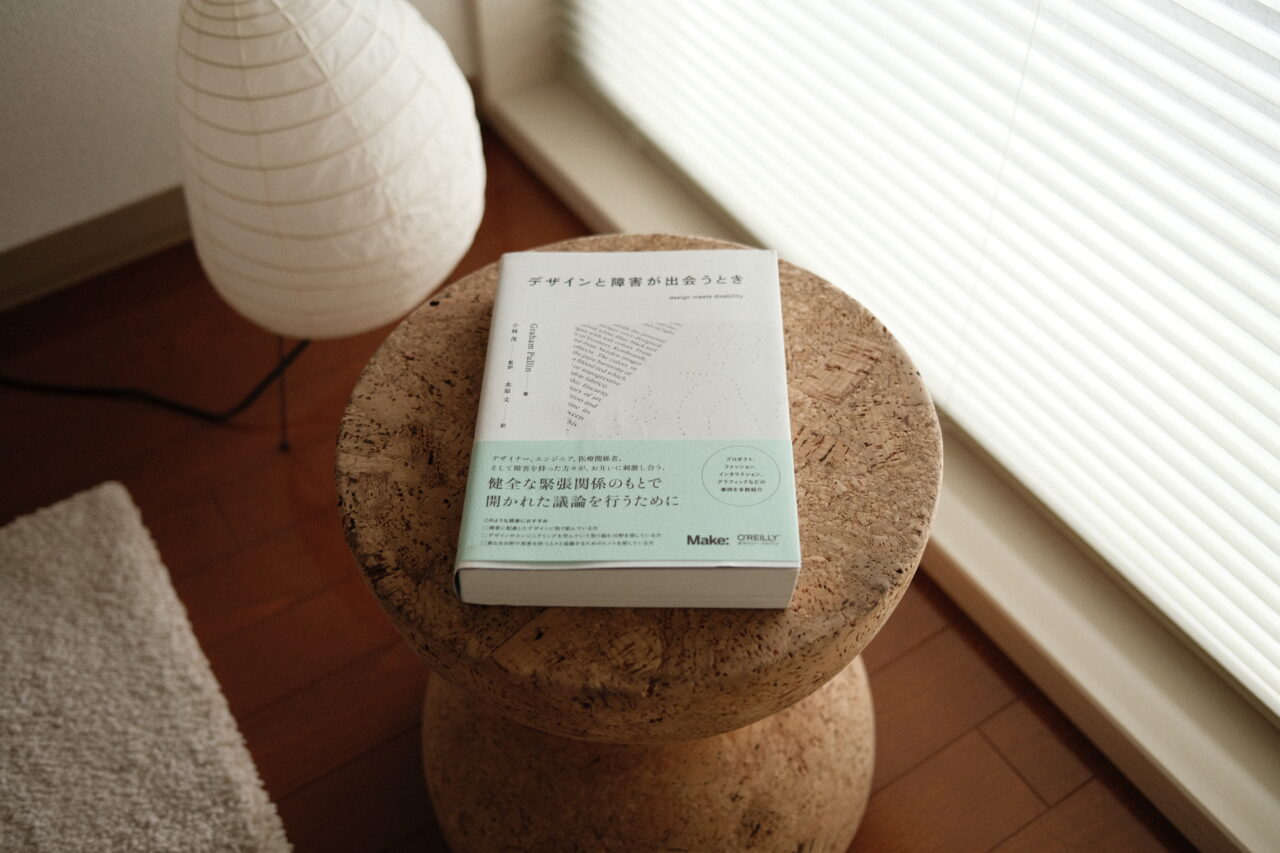引き算でブランドを創る|ブランディングとミニマリズムの関係性について考察してみる
2024.09.05

本記事はブランディングは引き算で作るのではないか?という可能性についてです。
ブランディングは色々な見方や考察があるので一概になんとも言えないですが、ミニマル思考のことを考えていたら何故かブランディングと繋がったので記事にします。
引き算とブランドの関係性について
- 強固なブランドには引き算が共通している
- 足して足して、そこから極限まで引いて残ったものがダイヤの原石
- 賛否両論こそ唯一無二のブランドになる
1. 強固なブランドには引き算が共通している
- やらないことを決める必要性
- 足し過ぎるとブランドとしての価値が薄まる
- 長期目線をもって選択する
Appleではスティーブ・ジョブズが復帰した際に当時のApple製品のほとんどを廃止したのは有名な話です。これは引き算によって可能性のある商品の開発だけに集中するためです。その結果iPhoneやMacなど革新的な商品が誕生して、Appleというブランドが確立されました。
スターバックスも日本進出の際に当時主流だったフランチャイズという手法を捨てて全て直営で行なっています。これはスターバックスの理念やサービスの品質を担保するためです。
ブランドとして確立されている企業を見ていると、やらないことを決めている企業が多いです。
しかし現代の社会では足し算が目立ちます。あれもできます、これもできますでは結局何も強みがない状態になってしまい、ブランドとしての価値は薄れてしまいます。
コンビニなども競合が出しているからという理由だけで新製品を出したり、その結果として差別化ができなくて似たような商品ばかりになって最終的に価格競争になってしまいます。
ファミリーマートがファミチキを出したからといって、ローソンがLチキを売る必要があるのだろうか?セブンイレブンがナナチキを出す必要があるのかをよく考えなければならないです。
世の中の問題の希少化によりどうしても大量生産大量消費の思考に陥りがちだが、勇気を持って何かを捨てるという選択をすることも大切です。
足し算思考は短期的に見ると利益もあるし理にかなっていますが、良くも悪くも色々と誤魔化せてしまいます。一方引き算思考は短期的にみると利益は無いし、一見非合理かもしれません。ですが誤魔化しが効かない分洗練されて、さらに長期的にブレずにブランドを構築することができます。
何か作るときは勿論目先の売上のことも大切だけど、一歩立ち止まって企業理念や個人の信念に反していないか、環境負荷や人的リソースをかけてまで本当に作るべきものなのかを考えなくてはならないです。
2. 足して足して、そこから極限まで引いて残ったものがダイヤの原石
- ブランドの正体は引き算で見つける
- コンサルティングでブランドを構築する
- 直感で決める勇気を持つ
いろんな経験や実績などを足してそこからいらないモノやコトを極限まで引いて残ったダイヤの原石を第三者に正しく認知してもらい、ファンになってもらうことがブランディングだと思っています。
もっと言うと、その残った何かを人は深みと呼んだり美意識と呼んだり、時にはWHYとかセンスと呼んだりしているのではないかと筆者は考えています。
ブランディングと聞くとトータルでコンセプトやロゴやWebを作成したりクリエイティブの要素のイメージが強いですが、ずっとどこかで違和感を感じていました。それはそもそもクリエイティブは足し算的な思考だからです。
この理論でいくと、ブランディングに最も重要なのはクリエイティブではなくコンサルティングなのではないかと思っています。コンサルは引き算の要素が多いです。今あるところから無駄な要因を引いて、ダイヤの原石を見つける手掛かりになります。
そう考えるとコンサルティング(引き算)により引いて見つけたダイヤの原石をクリエイティブ(足し算)により視覚化して認知してもらうことが理想的なブランディングです。
順番が大切で、まず我々は何者なのかをハッキリさせてから足していくとブランドとしてより強固になります。
そして現代では引き算により極限まで洗練させても存在意義やビジョンが不明確な状況が多いです。これはそもそも現代社会で解決すべき問題があまり無いことを表しています。
そんなに問題では無いことを無理やり問題にして、ビジネスと結びつけてしまっているということです。一言で分かりやすく言うと、それって本当に必要?ってことです。
市場調査や分析も大切ですが、それだけではビジョンやコンセプトは表面的になってしまいます。直感に頼って方向性を決めるのもある意味理にかなっている場合が多い気がします。
3. 賛否両論こそ唯一無二のブランドになる
- 誰からも愛されるブランドは存在しない
- 嫌われることは、好かれること
- どこかで尖ることの必要性
誰からも愛されるブランドは存在しない。それが筆者の考えです。
誰からも愛されるというのは裏を返せば誰からも愛されていないことと同等です。
逆に誰かから猛烈に批判されているブランドは、誰かから熱烈に支持されている証拠です。即ち、どこかで尖ることはブランドとして確立するためには必要なのではと思っています。これは企業でも人でも同じです。
そして沢山のものやことを捨ててきて信念の元動いている企業や人はアンチも多いですが、ファンも沢山います。誰でもあえて嫌われたくないと思うものですが、ファンの期待に応えることができるのであればアンチの声を無視する強さも大切なのかなと思います。
そしてある意味、本当に正しく認知されていればわりと好き嫌い分かれるものです。
逆に本当に正しく認知された上で、普通。というのがある意味1番怖いのかなと思います。(戦略として普通という認知をしてもらい場合を除く)
ラーメン屋の謳い文句として、10人の食べに来てくれたお客さんの中で1人でもまた来てくれればそれで良いというセリフがよくありますが、かなり的を得ているなと感じます。また食べに来てくれるファンに向けていつもと変わらぬ一杯のラーメンを作れば良いのです。
まとめ
足していくことは安心感もあり、やっている感も出て良いですが足す前に本当に必要なのかを判断することが良質なブランド形成に必要です。
そして足すことは意外と簡単にできてしまいますが、引くことは怖いし何かをやっている感じもあまりしません。でもだからこそ難しくて真似できないのだと思います。
もし自分や企業の本質を見抜いてダイヤの原石を見つけられたのであれば、それは唯一無二のブランドになりうるのかもしれません。
(筆者)