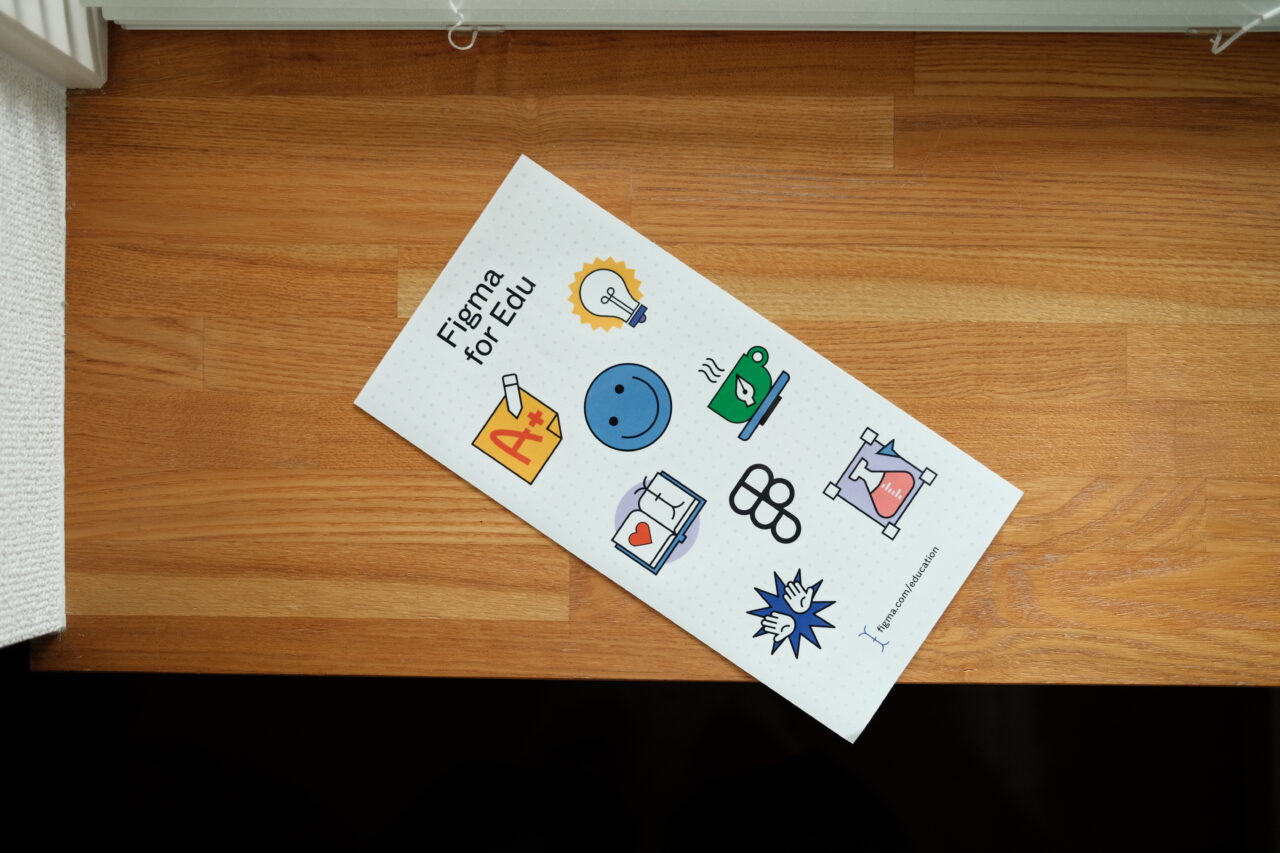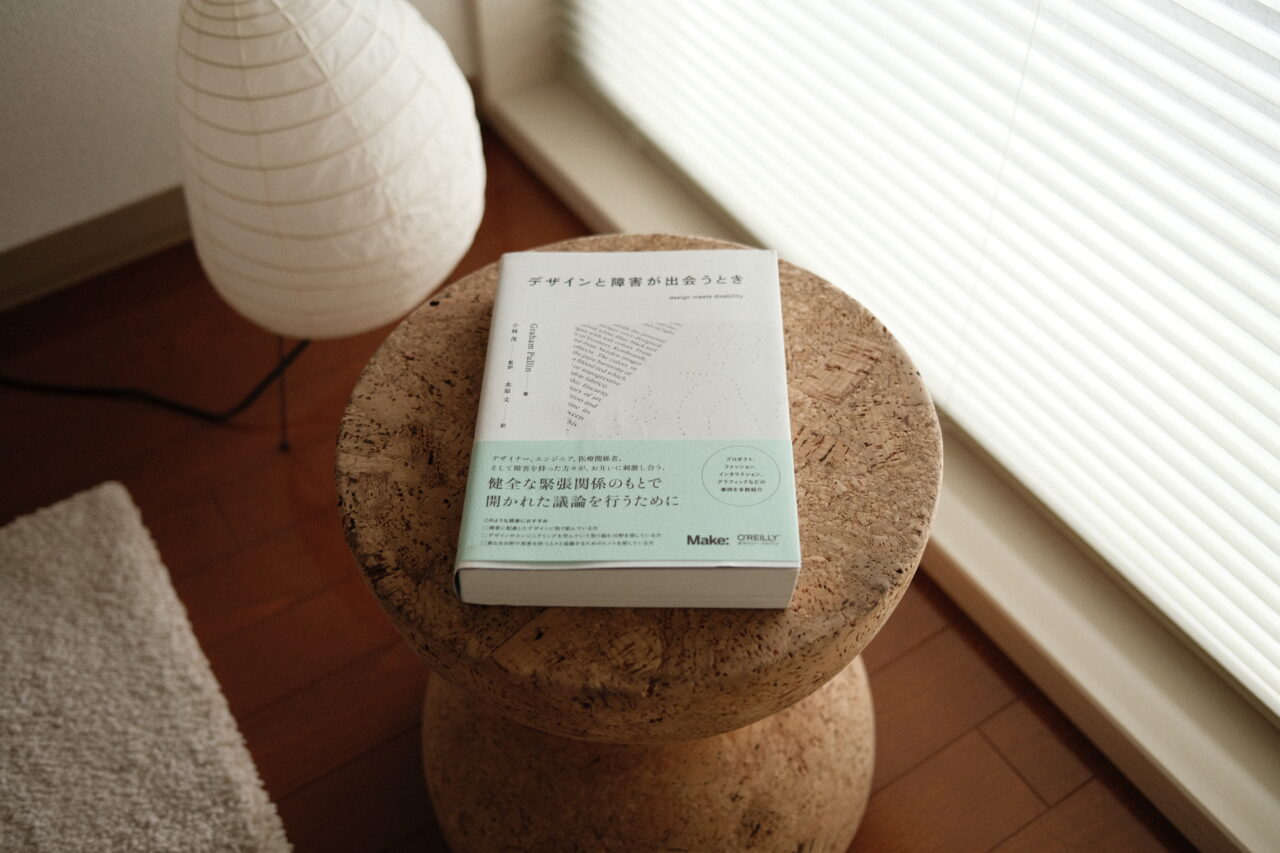守りの戦略|保守的な性格は最終的に攻めにも繋がるのでないかという話
2024.08.27
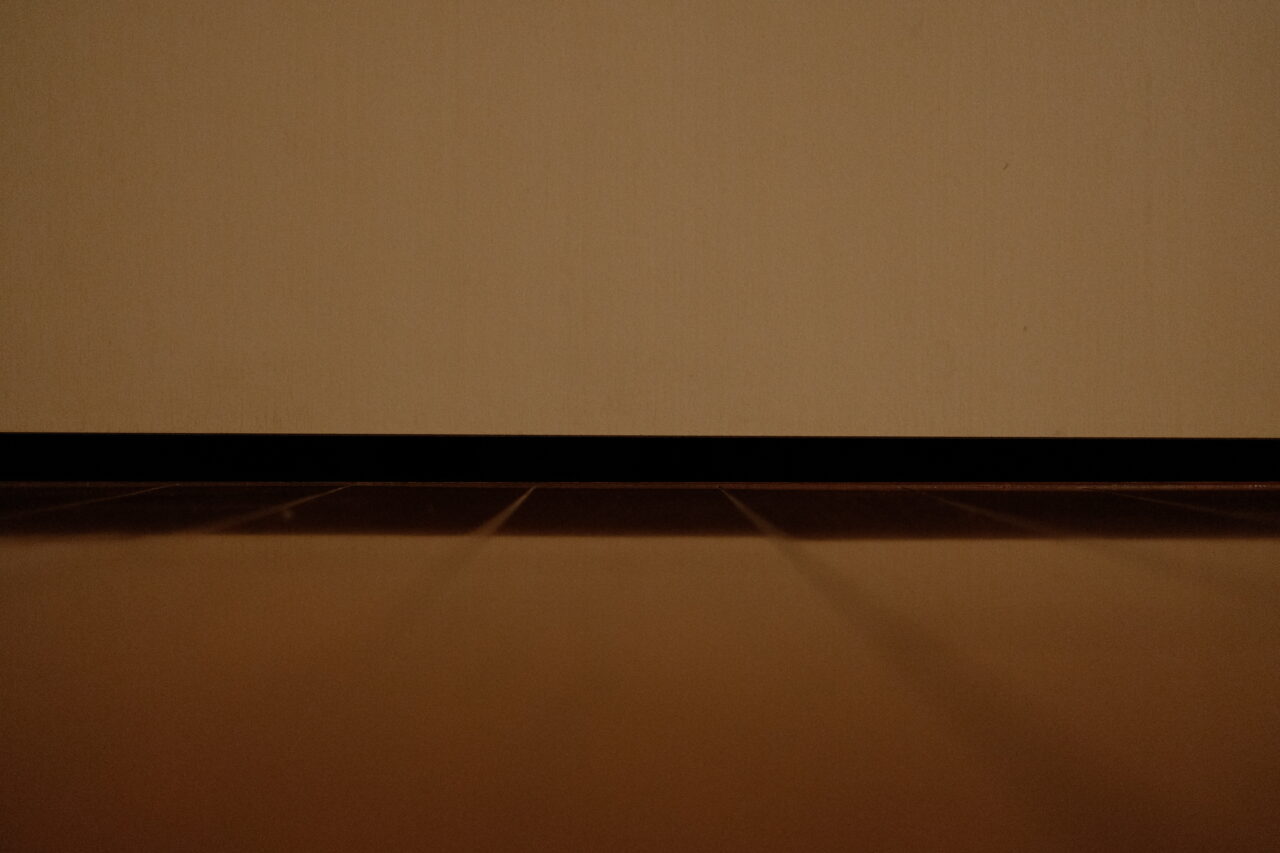
保守的な性格と聞くとなんとなくマイナスなイメージがありますが、そんなことはないと思っています。考えすぎて瞬時に行動できなかったり、攻めることができない自分に嫌気を感じることもあるかもしれません。しかし大事なのは、自分はどういう人間なのかをよく理解することだと考えています。
そして自分に合った戦略を立てて、仮設検証しながら少しづつ前に進むことができればどんな人でも自分らしい生き方ができるのではないかと感じています。”ミニマリスト”というわりと保守的な肩書きを持つ私が、保守的な性格は攻めにも繋ぐことができるのではないかと思う理由を解説していきます。
目次
- アインシュタインとバーベル戦略
- イソップ寓話から受ける保守の教訓
- 仮設検証で比重のバランスを探る
1. アインシュタインとバーベル戦略
投資の世界にバーベル戦略という言葉があります。バーベル戦略とはハイリスク・ハイリターンの資産とローリスク・ローリターンの資産など対照的な資産を組み合わせる手法です。つまり比較的安全性の高い90%を確保した上で、残りの10%はリスクをとった投資をするということです。
わかりにくいと思うのでここでは”キャリア”で置き換えてみます。世の中でよく言われているのが、会社員か個人事業かという選択です。会社員は雇用形態は安定していてリスクも少ないのですが、稼げる上限が大体見えています。なのでここでは仮に“守り”と呼びます。個人事業はハイリスクですがうまくいけば上限なく資金が入る可能性も高いです。なのでここでは“攻め”とします。
その場合例えば本業で税理士をする傍、趣味で陶芸作家なんかもできると思うんです。例えは適当ですが、とにかく守りを固めてからリスクを取って攻めるイメージです。このケースの場合、いきなり陶芸を本業にするのはとてもハイリスクなことがわかります。
そしてアインシュタインはまさにこのバーベル戦略の代表例だと言われています。アインシュタインは特許庁で審査官の仕事をしながら、暇な時間で「光量子仮説」の論文を書いたとされています。逆にいうと、アインシュタインの本業が研究だった場合、彼はノーベル賞を取ることはなかったのではないかと私は考えています。
もしその余白の時間があってこその創造性や発想だったと考えると、守りの思考は必ずしもマイナスに作用しないと言えます。
もちろん中には会社員でありながら攻めてる人もいるかと思うのですが稀なのではないかと感じていて、自分が何をやりたいのかをちゃんと理解していて会社員としてそれをできている人は少数だと思いますし、とても運が良い方だと思います。
2. イソップ寓話から受ける保守の教訓
保守的だけどコツコツと自分のペースで物事を進めることは実は誰にでもできることではありません。イソップ寓話でもそのような物語が沢山あります。
ウサギとカメの例
皆さんご存知かもしれませんが、ウサギとカメの童話を例にだします。念の為おさらいをすると大体こんなお話です。
ある日、ウサギとカメが競走をすることになりました。ウサギは足が速く、自分が絶対に勝つと確信していました。競走が始まると、ウサギはすぐにカメを大きく引き離しました。途中、ウサギはカメがとても遅いことに気づき、「少し休んでも勝てる」と油断し、木の下で寝てしまいます。
一方、カメはウサギのように速くは走れませんが、休まず一歩一歩前進し続けました。やがてカメはウサギを追い越し、ゴールに近づきます。ウサギが目を覚ますと、カメがゴールに迫っているのに気づき、慌てて追いかけますが、時すでに遅し。カメが先にゴールし、競走に勝ちました。
私がウサギとカメから学んだ教訓は、自信過剰にならずに物事に取り組む大切さです。ウサギはカメを見て競争していますが、カメはゴールをしっかりと見ていることがわかります。これは保守的にコツコツ進めることが最終的に勝つことに繋がる可能性もあるということだと思います。
アリとキリギリスの例
アリとキリギリスの話も保守的で堅実であることが最終的に良い結果として繋がった話です。
夏の間、アリたちは一生懸命働いて食べ物を集め、冬に備えていました。一方、キリギリスは夏の暖かい日々を楽しみながら、歌を歌って遊び、まったく働こうとしませんでした。アリたちに「どうしてそんなに一生懸命働くの?」と尋ねると、アリたちは「冬に備えているんだよ」と答えましたが、キリギリスはその忠告を無視し、「今を楽しめばいい」と言って過ごしました。
しかし、やがて冬がやってきて、食べ物がなくなったキリギリスは飢えて困り果てました。アリたちは夏に集めた食料を備蓄していたため、冬を快適に過ごしていました。キリギリスはアリたちに助けを求めますが、アリたちは「夏に歌っていたなら、冬にも踊っていればいい」と言って助けを拒みました。
目の前の快楽を楽しむのも大切ですが、計画的に物事を見るのはとても大切だと思います。しかし未来のために何か準備をしておくことは必須だと思っていて、私は得た教訓は備えあれば憂いなしということです。
どっちが正しいという問題ではない
私が伝えたいのはどちらが正しいという問題ではないということです。例えば先ほどお話ししたウサギとカメの話ですが、物語上ではカメが勝利しますがウサギはウサギの強みもあると考えています。
初速の速さとフットワークの軽さというところでカメには出せない魅力があると思います。この物語のその後を空想すると、ウサギはその失敗を自覚して次に活かすことができるのかというところが大切なのです。アリとキリギリスについても同じことが言えます。
3. 仮設検証で攻守の比重バランスを探る
ここまでは割と守備に比重を置いたお話をしてきましたが、中には攻めが得意な人もいます。試行錯誤を繰り返して、自分に適した攻守のバランスを見つけることが最も重要なのではないかと私は思っています。
極端な話、攻め100%でなんとかなる人はもうそのまま突き進むべきということです。というよりもそういう人は守りのことなんて考えていないものです。人物例を出すとホリエモンのようなタイプです。そしてこういう人達は試す数が尋常じゃなく多いので結果として成功しているケースが多いのは事実だと思います。
しかし守備型の人間がホリエモンの言うことをそのまま真に受けて攻めすぎると失敗する可能性が限りなく高いと思っていて、その人の性格や適材適所があるので全員が全員そんな思い切った行動はできません。
ですが失敗の大切さもよく理解しているつもりなので、行動しない方が良いと言っているわけではありません。いきなり大胆なことをしないで、軸足を固めた後にまずは小さく始めてみるのが得策なのかなという気はしています。少しややこしい話になってきますが、つまりは攻守のバランスをみて試行錯誤しながらどう頑張るのかを決めるのを頑張った方が良いという話なのです。
まとめ
保守的な性格であることはデメリットではなくその余裕が攻めに繋がるケースがあるという事と、自分の攻守のバランスを見極めて戦略を立てた方が結果として良い方向に行くのではないかというお話をしてきました。
私自身、とても慎重で臆病な性格だと思っていて正直リスクはあまり好きではありません。でもだからこそきちんと調べて計画を立てようとも思いますし、リスクを取る時にすぐに行動できる余裕と身軽さが欲しいということもあります。
というか話がひっくり返るかもしれませんが、攻めとか守りとかどうでも良いと思えるくらいが実は1番幸福なのではないかと思うくらいなのです。人の価値観は十人十色で深く考えすぎずに直感に委ねる選択も素敵なのかなと思っています。この記事が新たな付きになって誰かの役に立つと嬉しく思います。
(筆者)