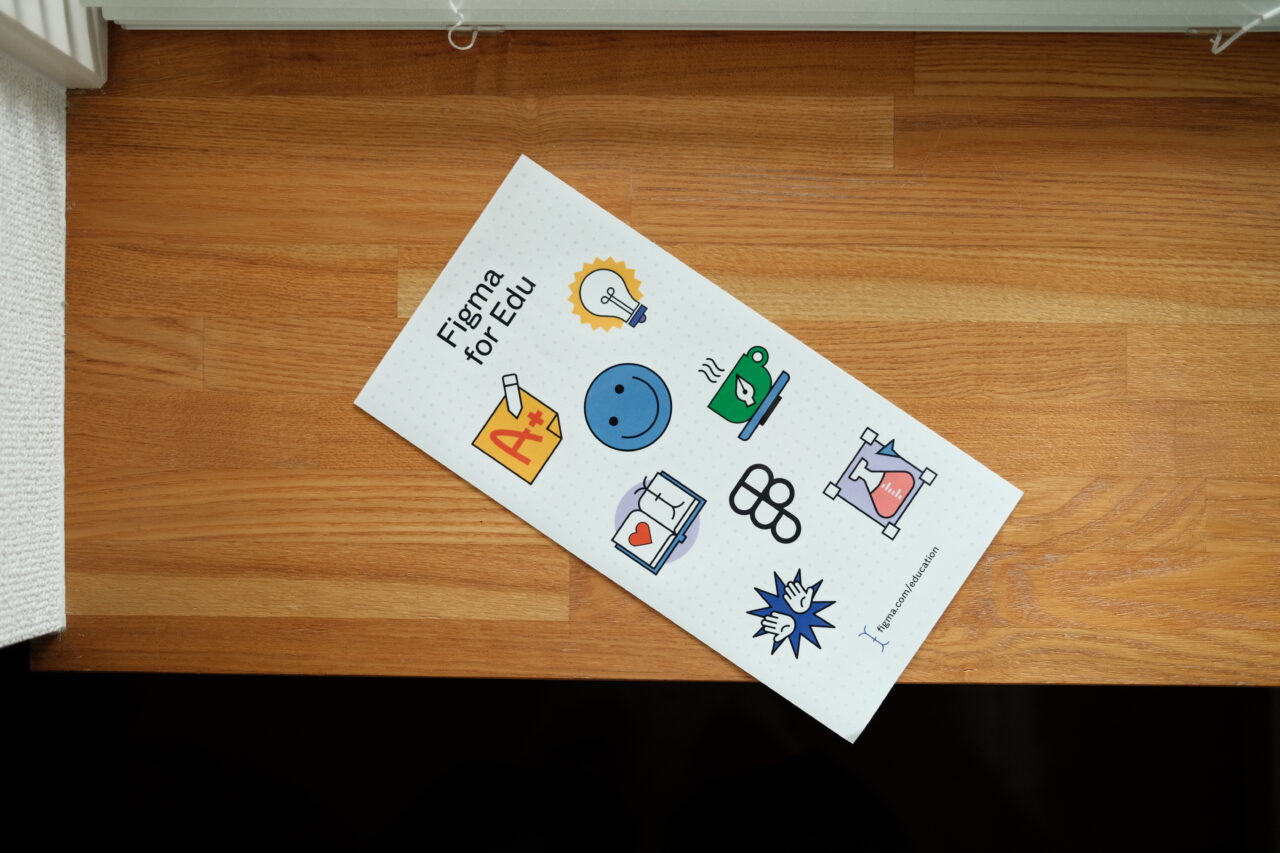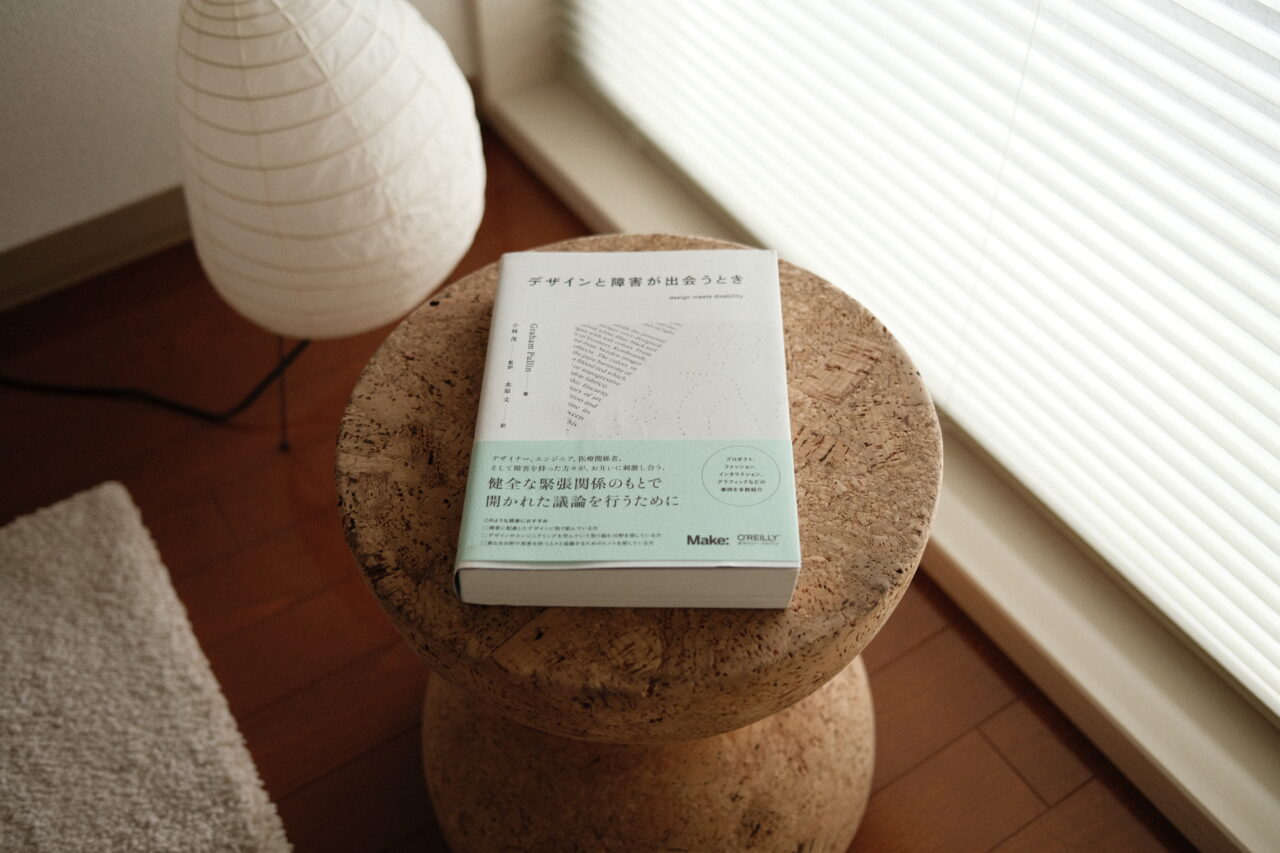勉強の大切さ|学ぶ習慣を止めないことが人生を豊かにすると思う理由
2024.09.05
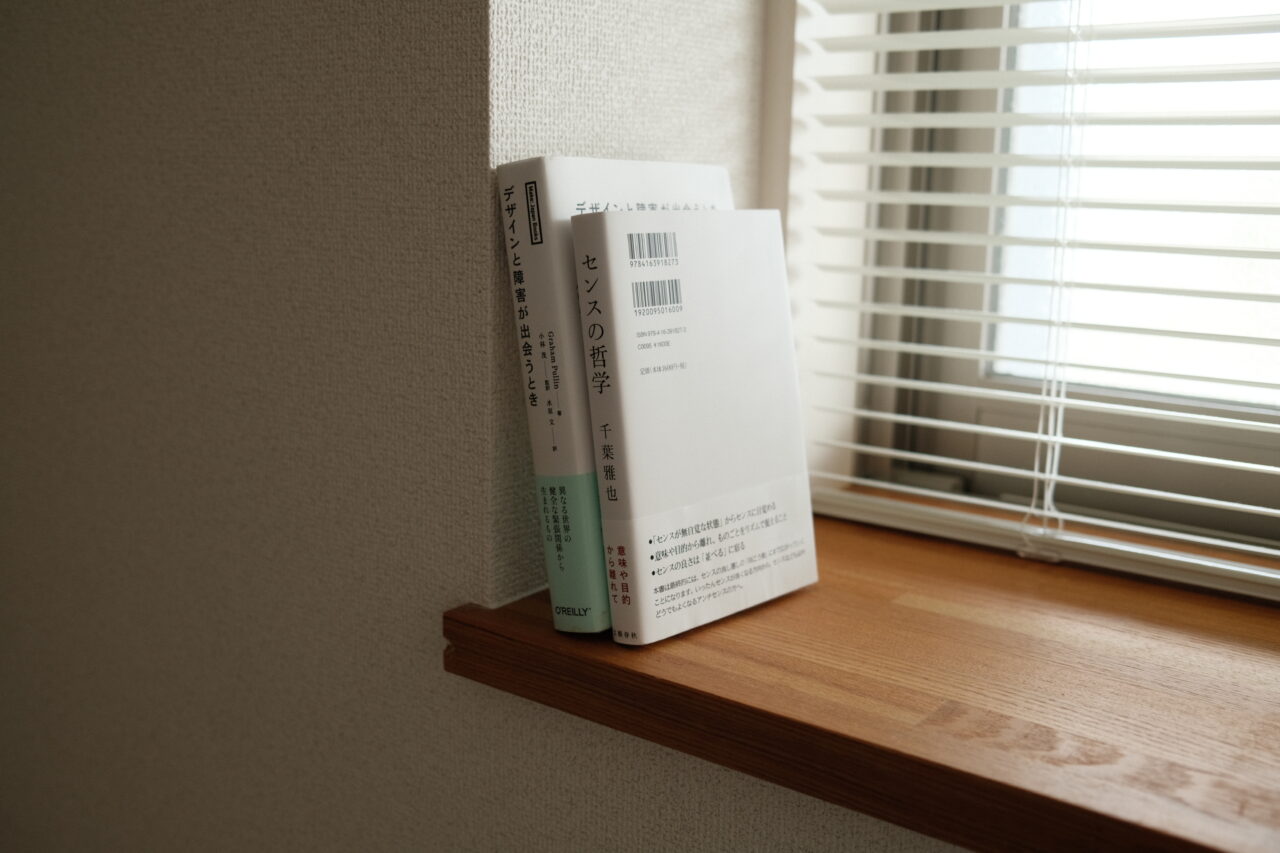
“勉強”と聞くととても嫌なイメージがありますが、有意義な暮らしをするのには必要不可欠だと思っています。というのも私自身学生時代は勉強が大嫌いで敬遠していたのですが、社会人になって学ぶことの大切さや深さを知り、今では単純に知識を取り入れるのが楽しくなっています。
そして質の良いインプットを心がけることによって自分なりの物事の良し悪しの判断軸もできるし、質の良いアウトプットにも繋がると考えています。勉強が大嫌いだった私が学びを継続することで人生が豊かになると思う理由について書いていきます。
目次
- 勉強することで騙されにくくなる
- 自分の興味があるジャンルを中心に学ぶ
- 質の良いモノは質の良いインプットから生まれる
1. 勉強することで騙されにくくなる
自主的に勉強する重要性
勉強をすることで、騙されることが少なくなります。言い方は少し良くないかもしれませんが、社会に出てみると勉強しないものは搾取され、勉強するものが有利になるような仕組みが多く存在します。そしてこういう知識は学校や職場では教えてくれないことがほとんどです。つまり自主的に勉強するしかないのです。
私自身こういう経験を実際にしてきました。一度体験することによって重大さに気がついて勉強することもあるので全てのパターンに該当するわけではないですが、自分を守るためにそういうリスクを回避する心構えは大切だと思っています。
疑う意識は悪ではない
たとえばスキルアップを売りにした情報商材などもその類だと思っていて本当にスキルになるなら全然問題ないのですが、実際購入してみたら高額の割に内容が薄いなど結構あります。世の中の頭の良い人たちはいかに自社の商品を売るかを常に考えてマーケティングしています。
他にも限りなく黒に近いグレーの手口を使ってあの手この手で騙してこようとする人も信じられないかもしれませんが存在します。相手を疑う意識を持つことは大切だと思っています。私の好きな漫画、ライアーゲームからの引用です。
人は疑うべきだよ。多くの人は誤解している 「人を疑う」とはつまりその人間を知ろうとする行為 「信じる」その行為は紛れもなく高尚な事だ…だがね多くの人間が「信じる」の名の下にやってる行為は実は他人を知る事の放棄。言い替えれば無関心だ。
引用:集英社出版発行LIAR GAME(甲斐谷 忍 著)
疑うことは悪いことではなく、本当に悪なのは無関心なのです。疑うことから始まる学習もあります。つまりどんな些細なこともにも疑問を感じ取るセンスやそれを調べる癖などって豊かで充実した人生を送るのにとても重要だと今となっては感じています。
2. 自分の興味があるジャンルを中心に学ぶ
どんなに離れたジャンルでも自分の興味や関心はどこかで必ず繋がってくると私は思っています。それを人は直感と呼ぶのかもしれませんが、そういう体験をしたことがある人は多いのではないでしょうか?なので、私はとりあえず興味のあることを深く掘り下げて学ぶのが一周回って合理的なのかなと感じています。
もしそのジャンルに飽きて辞めたとしても、数年後新たに勉強していたことが偶然共通している部分があったり、その繋がりに感動することも出てきます。例えば私の例で言うと私の興味のあるジャンルややっていることはこんな感じです。
- 踊り
- 哲学
- 障害
- 健康
- アート
- インテリア
- デザイン
- エンジニアリング
- アニメ
障害×デザイン
これは一例ですが、掛け合わせとして“障害”と”デザイン”があります。訳あって昔から発達障害についてずっと調べていたりするのですが、数年経った今その繋がりを感じています。
たとえばWebデザインにはWebアクセシビリティという概念があります。Webアクセシビリティとは、「年齢やからだの条件、利用するインターネット環境に関係なく、提供される情報に問題なくアクセスし、利用することができる」ことです。
しかし当時の私はこんな概念は知らなかったのですが、Webを勉強するにつれてここに辿り着きました。つまり私が昔打った点である“障害”と、現在の仕事である“デザイン”が数年経って実は線で繋がっていることに気がつくことになります。そしてどんな人にも問題なく情報が届いてほしいと言う思想がこのブログの“デザイン”や”哲学”にも反映されています。
関連記事:アクセシビリティ
インテリア×デザイン×アート×障害
インテリアで言うと私の家にある大好きな椅子も元々は戦争に使う足の骨折時の副え木からインスピレーションを受けていたりします。これは“インテリア”と”デザイン”と”アート”と”障害”とたくさんの繋がりが見つかった例です。
椅子は様々な視点から合理的かつ美しく作る必要があるし、今思えばその歴史背景や思想、機能美が私の心に響いたのではないかと感じています。そしてこの感性は私のモノ作りに関する意識を大きく動かすきっかけになりました。
点を繋ぐ重要性
深く学習することによって、この点の数を増やしていくことにより唯一無二の仕事や生きる目的みたいなのができていくのではないかと私は感じています。学ぶ習慣を止めないことは点を繋げるという意味でもとても大切です。
未来に先回りして点と点をつなぐことはできない。君たちにできるのは、過去をふり返ってつなげることだけだ。だからこそ、バラバラの点であっても将来それが何らかのかたちで必ず繋がっていくと信じ続けることだ。
引用:スティーブ・ジョブズ(1955~2011・Apple創業者)2005年スタンフォード大学卒業祝賀会スピーチより
3. 質の良いモノは質の良いインプットから生まれる
「目より先に手が肥えることはない」という言葉があります。つまり、「良し悪しを見抜く”目”を養わねば何かを生み出す”手”の成長は望めない。」ということです。どの業界でもそうですが、まずは世の中で一流と呼ばれているものを洞察するところから始めるのがセオリーです。
自分の目指す場所が高ければ高いほどそうした方が良いと感じています。そして一流を知ることによって”普通”もわかるようになってくるものだと思っています。そしてこの普通を知ることによってものの見方を分析する能力を育てることができます。つまり視野が広くなるのです。
たとえば一流を知っておけば、“あえて普通にする”なんてことも可能になってくる訳です。しかし学習せずに一流を見ないと“普通を一流だと思い込む”という現象も起きてしまうと考えています。そしてこのレイヤー間のギャップがセンスの良し悪しを決めるものだと思っています。
日々の勉強を継続することは良いインプットにも繋がります。良いインプットはモノ作りの品質を高めてくれるものだと感じます。そして良いインプットによって生まれるアウトプットは間違いなく今の人生を豊かにしてくれるものだと思っています。
私が日々の学習について思うことは、何でもかんでも取り入れればそれで良いということではないということです。大事なのはその知識を自分の中でどう落とし込むかだと思っています。一般的には良いとされていることでも自分には合わないこともあるし、逆も然りです。横目で見つつ何を学ばないのかを決めることもある意味学習なのかもしれません。
まとめ
勉強嫌いだった私が、学ぶ習慣を止めないことが人生を豊かにすると思う理由を書いていきました。散々偉そうなことを言っておきながら私自身まだまだ未熟で勉強が足りていないなと思います。
ただ、“世の中にはまだ知らないことが沢山ある”と感じられることはとても贅沢なことだと思うので、探究心やワクワクを忘れずに日々勉強を継続しようと考えています。この記事を読んで勉強の大切さに気がつき、学びを継続してくれる人がいたらとても嬉しく思います。
(筆者)