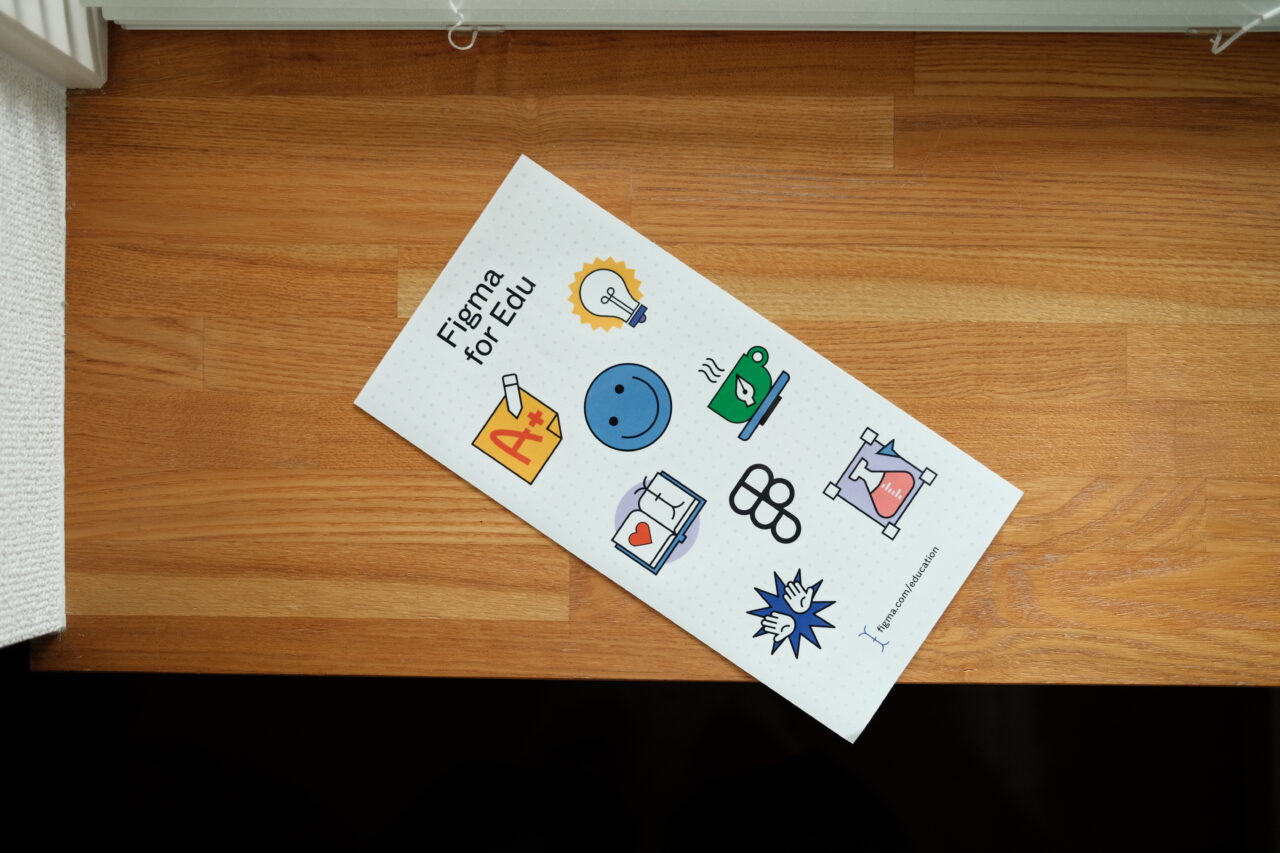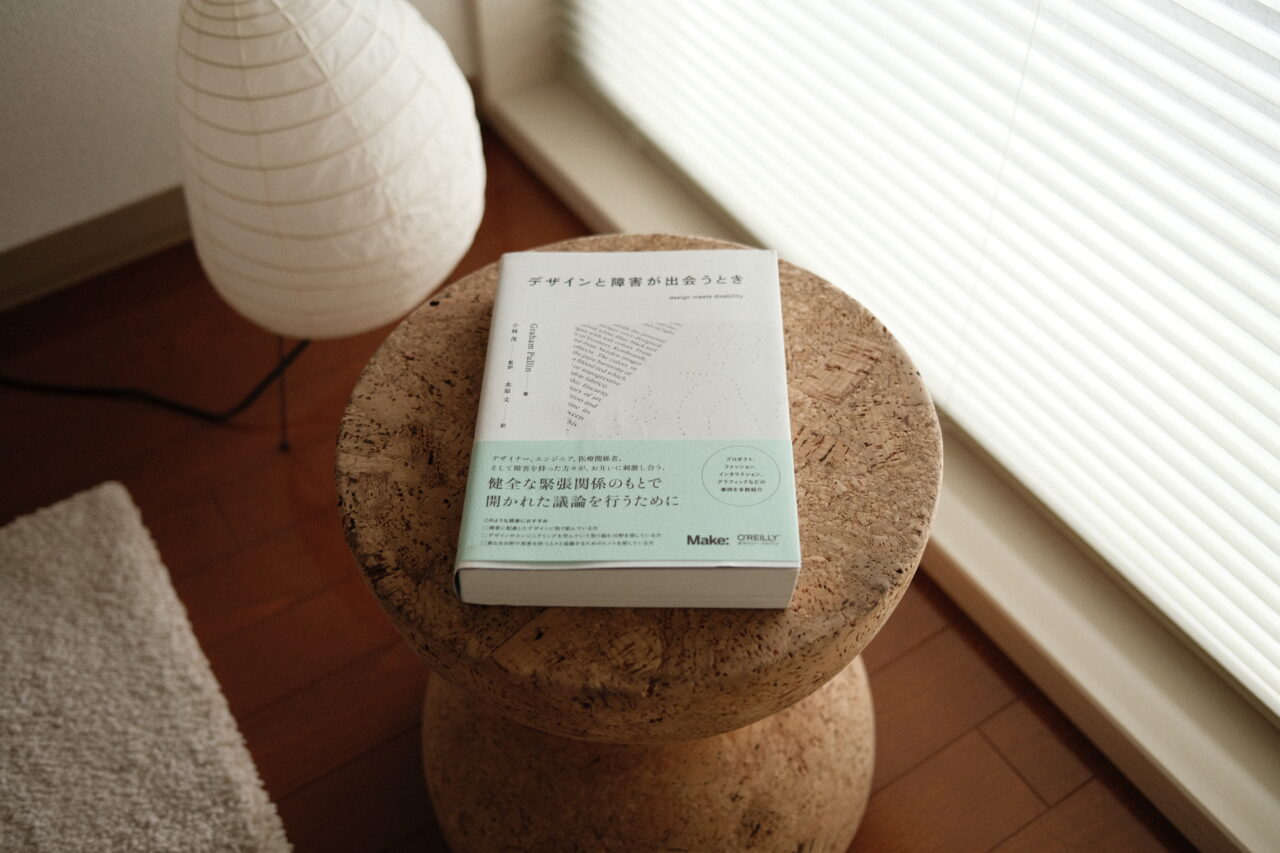優秀さの正体|評価は“周波数”で決まるという仮説を立ててみる
2025.07.29

「優秀な人材」って言葉、たまに見かけると思います。でも私はその言葉にちょっと違和感があります。なぜなら、どんな人でも“優秀”であると同時に“無能”でもあると感じているからです。
もちろん、人には得意不得意もあるし、能力に差もあるとは思います。ただ、自分がこれまで仕事や人生の中で体験してきたことを踏まえると、それ以上に評価のされ方って“周波数”によるものなんじゃないか?という仮説を持つようになりました。
1. 優秀さは“絶対的”なものではなく“周波数的”なもの
たとえば企業で「この人は優秀だ」と評価されている人が、別の組織では全く評価されない…そんなことはよくあります。これは能力がないからではなく、その場所の“周波数”とズレているから起きる現象だと思っています。
言い換えれば、「優秀さ」とは絶対的なものではなく、その場にいる人たちと周波数が合っているかどうかで決まるのではないかということです。
1. 周波数のズレが生む誤解
たとえば、あるスポーツに人生をかけて努力してきた人がいたとします。その競技の世界では「優秀」として知られているかもしれないけれど、その外の世界に行けば「すごい人らしいけど、よく分からない」という扱いになる。場合によっては、スキルや成果に見合う評価をされないこともある。
これは完全に周波数のズレによる誤解だと思います。ラジオのチューニングのように、周波数がズレていると、ノイズが入ったり、何も聞こえなくなってしまう。
評価される・されないは、「誰と、どこにいるか」で決まる。その現実を無視して「能力がない」と片付けてしまうのは、ちょっと乱暴な気がしています。
2. 波長が合えば、誰でも「優秀」になり得る
シンプルに考えれば、「優秀かどうか」は“その人が今どこにいるか”で変わる。私はよく「ライオンは陸では百獣の王だけど、海ではただの猫」という例えをします。
ライオンは陸という“周波数”の中で最適化されているからこそ王になれる。でも海ではその強さを発揮できない。つまり自分に合った“環境”こそが、力を引き出す装置なんですよね。
もちろん、適応力が高ければ違う周波数でも戦えるかもしれない。でも、それには膨大な労力がかかるし、そもそもすべての人に適応を求めるのは酷な話です。
だから私は、自分の周波数を調整するよりも、自分に合った周波数の場所を選ぶ戦略の方が現実的だと思っています。
2. 周波数と経験値の関係:違和感の正体
人は成長とともに、周波数が変わります。昔は合っていた人間関係が合わなくなったり、価値観が合わなくなったり…。それって、単に“ズレ”が生じてきた証拠なのだと思います。
周波数がズレていると、「なんか話が噛み合わない」「許せない」「やたら悪口を言われる」「やたら失敗する」といった違和感が生まれます。
だからこそ、自分の今の周波数を知るためには、その違和感に気づく力(=洞察力)が必要です。そしてそのセンスは、表面的な出来事に対する分析ではなく、経験を通じてしか磨けないのだと思います。
3. 評価を求めずに環境を選ぶ勇気を持つ
「優秀さ」って、実は中身ではなく“どこで・誰と・何をしているか”で大きく左右されるんじゃないかと思っています。
だからこそ私は、「どう評価されるか」よりも「どんな周波数の場所に自分を置くか」が大事だと感じています。自分が本来持っている力を発揮できる“波長の合う場所”を選ぶこと。それは逃げではなく、立派な戦略です。
人生は一度きりのゲームです。自分の“周波数”を信じて、しっかりと勝てるフィールドで戦っていきたいですね。
(筆者)